【注意】下記は、私の受験時の考え方によるものであり、完全な解答ではないので、参考程度にしてもらえるとありがたいです。
解き方は、『知識(知ってるか知らないか)』『思考(基本的な考え方による判断)』『国語(文章からの判断)』の3種類で分けてみました。
問題
問150
9歳の男児A、小学3年生。Aは、注意欠如多動症/注意欠如多動性障害〈ADHD〉と診断され、服薬している。Aは、待つことが苦手で順番を守れない。課題が終わった順に担任教師Bに採点をしてもらう際、Aは列に並ばず横から入ってしまった。Bやクラスメイトから注意されると「どうせ俺なんて」と言ってふさぎ込んだり、かんしゃくを起こしたりするようになった。Bは何回もAを指導したが一向に改善せず、対応に困り、公認心理師であるスクールカウンセラーCに相談した。
CがBにまず伝えることとして、最も適切なものを1つ選べ。
① 学級での環境調整の具体案を伝える。
② Aに自分の行動を反省させる必要があると伝える。
③ Aがルールを守ることができるようになるまで繰り返し指導する必要があると伝える。
④ Aの年齢を考えると、この種の行動は自然に収まるので、特別な対応はせず、見守るのが良いと伝える。
解くときの考え方
解き方:思考
キーワード
「注意欠如多動症/注意欠如多動性障害〈ADHD〉と診断され、服薬している」
「待つことが苦手で順番を守れない」
「Aは列に並ばず横から入ってしまった」
ADHDなどの発達障害の診断がされている生徒に対する考え方として、
「その子の特性として考慮し、正そうとしない」
という考え方をします。
SSTなどもありますが、これは担任の先生にするアドバイスではないと思っています。(ここまで担任の先生が受け持つと負担が大き過ぎます。)
また、文章にあるAの行動はADHDによく見られるものなので、それを正そうとする手段は望ましくない。
① 学級での環境調整の具体案を伝える。
→環境を改善、調整することが効果的であり、適切であることが多いです。〇。
② Aに自分の行動を反省させる必要があると伝える。
→Aの特性なので、反省させることは自己肯定感を下げるだけで、行動の改善にはつながらない可能性が高い。×。
③ Aがルールを守ることができるようになるまで繰り返し指導する必要があると伝える。
→②と同じ理由で、×。
④ Aの年齢を考えると、この種の行動は自然に収まるので、特別な対応はせず、見守るのが良いと伝える。
→ADHDによく見られる行動の特徴なので、×。
ADHDを知らないという方には難しかったかもしれません。
発達障害関連の問題は出題頻度は高いと思われますので、必ず抑えておきましょう。
解答:①
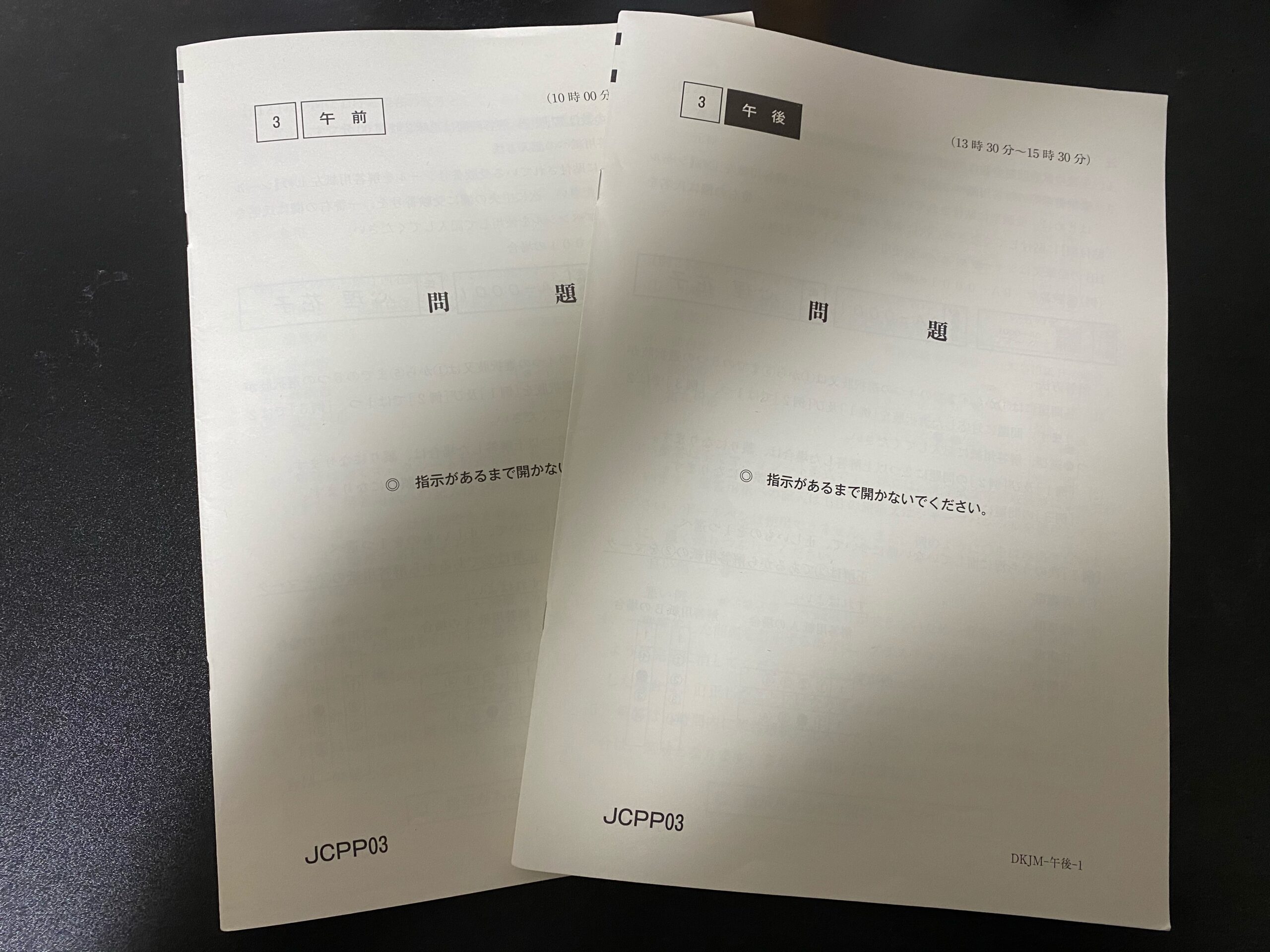
コメント